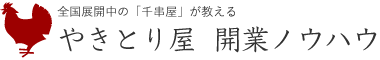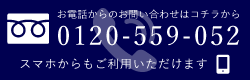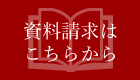飲食店経営では、「美味い物」を「きちんとしたサービス」で提供していれば、お客様が入り、売上があがり、儲かるだろう!と思っている方も多いのではないでしょうか。また、「飲食店は日銭が入るから、資金管理が楽だよね!」などと言われることもあります。しかし、どんぶり勘定で儲かるほど甘い世界ではありません。
ここでは飲食店が長く経営を続けるための数値管理について、20年の焼き鳥屋経営に基づいたリアルな話をしていきます。
Contents
気がつけば火の車。日銭商売の飲食店経営の難しさ
飲食店は現金商売です。毎日現金が入り、ついつい気が大きくなりがちです。そのため不要なものを購入してしまったり、大盤振る舞いをしがちになる経営者が多くいます。
しかし、日銭は入りますが、逆の言い方をすれば、まとまったお金は入ってきません。そして、支払いは月末にまとめて払います。例えば人件費、家賃、仕入れ、光熱費など。税金に関しては1年分をまとめての払うこととなります。つまり、きちんと現状を把握しながら経営をしなくては、あとから苦しむことになるのです。
「目の前に小銭はあるのに、月末になると苦しい」というのはよく聞く話。それが積もりに積もって、閉店という望まない結果につながる店舗が多いのです。「そうはならないようにする」という人も多いのですが、この“ズレ”に気づかずに経営を続けてしまうと、気づいたときには資金ショート寸前。店舗閉鎖を余儀なくされるケースも少なくありません。
特に脱サラと言われる月給もらっていた人たちや、飲食店をやっていた人でも料理担当で、あまり現金に触れなかった人たちの多くが陥ってしまう飲食店の罠と言えるでしょう。この“飲食店特有の資金感覚”をつかむことが重要なのです。
毎日、利益がいくら残っているか、大切なのはキャッシュフローを読む力
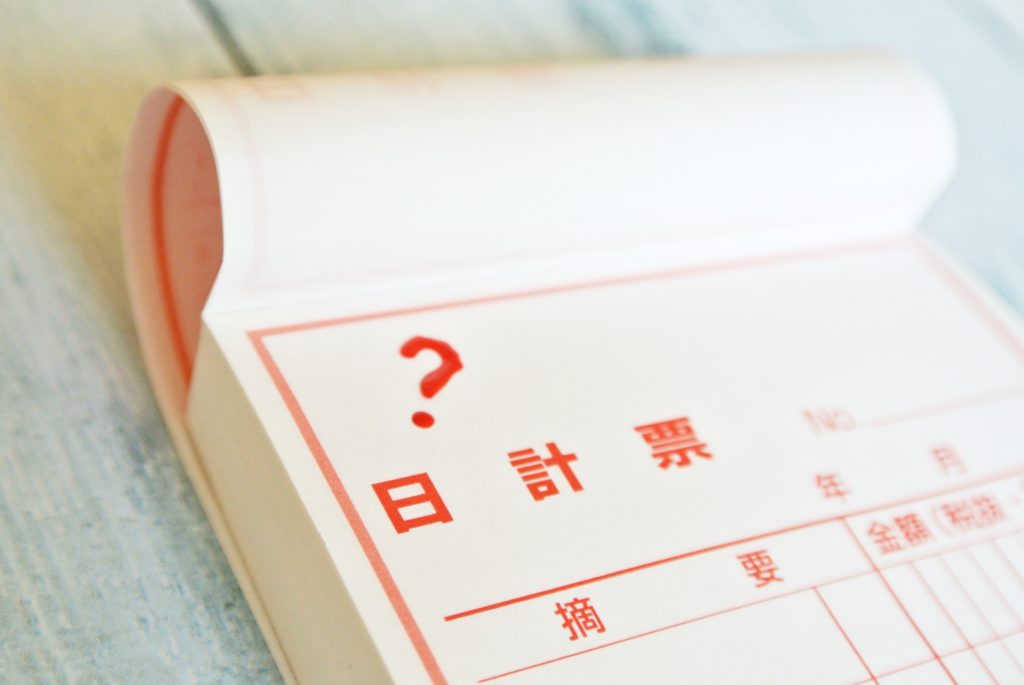
飲食店経営では、固定支出(家賃や光熱費など毎月ほとんど変わらない金額の支出)に関しては意識することなく運営し、FL管理(F:食材原価率・L:人件費率)を徹底することによって、日々の利益を明確にしていきます。毎日、日銭が入金されて現金が手元に残りますが、その現金の内、いくらが利益なのか?を把握する必要があるのです。
特に最近は、クレジットカードや電子マネーで支払いをする人が増えており、正しく管理をしないと経営はさらに混乱します。
2023年以降、インボイス制度や電子帳簿保存法の影響もあり、小さな飲食店でも「現金の流れ=キャッシュフロー」を意識しようと叫ばれるようになりました。ですが現状を見ていると、数店舗経営しているオーナーでも勢い任せで、正しく数値を把握していない危ない経営をしている人を見かけます。これは非常に残念なことです。
「今日の利益」を毎日見える化する
一見売上や現金があっても、今日はマイナス収支だったなどということも珍しくないのが飲食店。現金という観点で言えば、多くの来店があったのに全ての人がカード払いだったために、現金がないという日もあります。そんな中で日銭商売を成り立たせるためには、毎日現状を把握することが重要になってきます。
これはお店を2年3年と経営していれば自然とわかる数字と言われてきましたが、めまぐるしく変化する経営環境では勘に頼ることほど危ないことはありません。まして、はじめてオーナーになったという人は、なおさらです。正しい数値、特に利益を把握することの大切さを心得てください。
例えば千串屋では、加盟店様に日計表という名目で管理表を提供し、簡単に今日の利益を計算できるシステムを提供しています。レジ精算時に電卓さえあれば5分で計算できます。多忙な店舗の運営の中での作業。これくらい気軽なシステムでなければ続きません。日々の積み重ねが利益確保の着実な道。毎日の収支を把握するように努めてください。
POSレジを導入し、現状を正しく把握する

単純な売上利益管理だけでなく、客単価やFD比率(Food:食材、Drink:ドリンクの売上構成比)、どの商品が何個売れたか?などをすべて把握できなければなりません。そのためには、POSレジの導入が必要でしょう。
POSレジを導入することで、手軽に売上分析・原価分析ができる時代になりました。
- 商品別・時間帯別・スタッフ別の売上管理
- 原価・人件費と連動した収益性の分析
- 回転率や客単価の推移
- シフトコストとの連携でFL管理まで自動化
これらを使って管理機能を高めることが重要です。
FD比率を崩さない=生き残れる飲食店の必須条件
飲食店経営で儲けを出すのにドリンクは重要な存在です。原価率が低く、つくるのに手間もかからないからです。逆に言えば、FD比率が崩れたお店は、飲食店として成り立ちません。
地域事情等を考慮しながら出店していますが、やはりエリア独特の癖はあります。その癖を考慮し、メニューに反映させていきながら利益を確保するには、売上データを分析する必要があります。これも長年お店を経営していれば感覚的に理解し、メニューやサービスに適時繁栄できるのかもしれませんが、通常の飲食店では、それを身につけるまでに閉店してしまいます。
そのため、千串屋では定期的に売上データを分析し、メニュー構成や価格調整を柔軟に対応するよう指導しています。
また、うまく感じ取ることができないために、「お客様の言いなり運営」(お客様のあーした方がいい、こうした方がいい・・・という要望をそのまま受け入れ、結果的に利益を生み出せない店)に陥ってしまいます。そうならないためにも、IT技術を駆使して客観的に実数を把握し、経営に活かすことができるシステムを採用することは欠かせないのです。
労務管理システム。書類武装なくして、経営はできない
労務管理には、大きく2つの柱があります。
- 給与など雇用関係に関する帳票類の書類武装
- マニュアルや教育関係に関する帳票類の書類武装
経営者様としては、上記1・2の社内規則や教育マニュアルなどの書類武装をしなくてはなりません。これを持たずして経営者とは言えません。
しかし、こちらの資料を作成するには、膨大な作業が必要となります。就業規則1つ作るにしても、給与規定を作るにしても、マニュアルを作るにしても時間と専門知識が必要となり、中々着手しにくいのが現実です。そのため、書類がないままスタートしてしまいます。すると、ますます後回しとなり、後でトラブルに巻き込まれてしまうのです。これについては後回しにせず、早い段階で揃えておくようにしてください。
給与など雇用関係に関する帳票類の書類武装について

雇用に関する書類=オーナーを守ることに直結します。
昨今の雇用情勢では、残業時間や残業代が重要視されており、すぐに「あそこはブラックだ」などと世間でも騒がれることが多くなりました。アルバイトが店舗を訴えるようなケースも出てきています。このような場合、経営者は従業員から訴えられる立場となります。雇用契約書などの書類を用意せず、「給与だけ渡せばいいだろ!」というスタンスでは、従業員から残業代やオーバー労働などで訴えられてしまうのです。
また、そのような状況では他の従業員の働く意欲にもつながりません。人材の確保もしにくくなりますし、できるスタッフでも会社の未来が見えないために退職してしまいます。そこで、これに対抗するための書類を用意することを「書類武装」と呼んでいます。
弊社のFCパッケージでは、雇用に必要な資料一式をマスターデータとしてお渡ししております。さらに、そのデータの中には、飲食店ならではの勤務形態に合わせた給与形態や就業規則に関してのシステムやノウハウが織り込まれています。長年の経営経験を活かした資料一式ですので、初めての飲食事業でも、長年蓄積されたノウハウを織り込んだ規則を作ることが可能です。
飲食店の勤務形態は特殊で、社会保険労務士に頼んで制作しても経営の実情に合わせた書類はできにくいと言われており、自店にあっていないケースが多くあります。その点、弊社がお渡ししている資料は、書類内の会社名を「御社の店名や社名」に変更するだけで使えてしまうほどのものです。これであれば、作成に労力を使うことなく、スピーディに作成することができます。ご興味のある方は連絡をいただければと思います。
「数字がわかる経営者」こそ、飲食業の勝者
料理がうまくても、接客が良くても、数字が管理できなければお店は続きません。
逆に、数字さえ見えていれば、多少のトラブルや変化があっても軌道修正ができるのが飲食店です。
「現金が入ってくるから大丈夫」
「来月の支払いはその時考える」
──このような感覚で経営していると、気づけば赤字。経費や人件費が膨らみ、税金が払えず、店舗は追い込まれます。
それを防ぐのが、「毎日の数値管理」=地味だけど確実な利益確保の方法です。
数字を武器にした飲食店こそ、変化の激しい時代でも生き残っていけるのです。
こちらに、千串屋で使っている帳票類について記していますので、ご参考になってください。