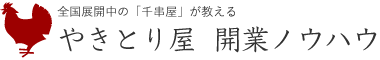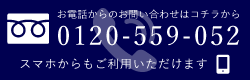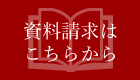長く続いたデフレの影響により、さまざまな業種・業態が混乱の中にあります。飲食業も例外ではなく、食材の値上げを「商品価格に転嫁できる店」と「そうでない店」に分かれていると感じています。
焼鳥屋について言えば、低価格を特徴にしている店舗は後者であることが多く、価格を上げることが命取りになることも少なくありません。また、そう感じているから値上げはできないと思っている店舗もあるでしょう。
では当グループはどうかと言えば、しっかりと値上げを実行しています。
ここでは、値上げと経営数値に対する考え方を【経験値+焼鳥屋20年の経験値】を元に書かせて頂きます。
単なる値上げはお客様の納得を得られない

値上げはするべきですし、私たちもグループでも値上げをしています。ただし、単に値段を上げるだけではお客様の納得は得られません。そこで私たちは「付加価値の提供」に力を入れるようにしています。
以下に例を挙げます。
・居心地のよい店内空間
・丁寧で感じのよい接客
・スマホから直接注文できるモバイルオーダーの導入(注文ストレスの軽減)
・高級感のあるブランド皿を使用して商品価値を演出 など
細かい点は企業秘密ですが、他にもたくさんあります。ようは工夫の積み重ね。お客様に「値上がりしても、この価格なら納得できる」と思っていただけるよう意識しているのです。
値上げにはこの発想が最も重要と考えています。
コスト削減は慎重に
食材費が高騰すると、値上げの前に「コスト削減策」に力を入れ、値上げを回避しようとする経営者がいます。これも大切なのですが、インフレ時に過度に力を入れるのは考えものです。
たしかにコスト意識は大切ですが、それが取引先や従業員への過剰な圧力となると、結果的にマイナスになります。
たとえば……
・納品業者に対して頻繁に値下げ交渉をする
・必要以上に仕入れ先に厳しく接する など
こうした行動は、「あの店はうるさい」「付き合いにくい」と思われてしまい、信頼を損ねかねません。
物価が高騰している今は、仕入れ価格が数か月毎に変動するような時代です。食材によっては毎月なんてこともあります。
そのため、「値下げ交渉は落ち着いてからで十分」くらいの姿勢が現実的で賢明です。具体的に言うなら、半年に1回程度がよいでしょう。それより早いと、仕入れ業者に嫌われるだけです。
価格にアンテナを張っておくことは大切ですが、価格交渉にエネルギーを割くよりも、コストパフォーマンスのよい仕入先を探したり、他社の動向を知ろうという動きのほうが効果的です。
値上げは“技術”である
「値上げ」には技術が必要です。ただ値段を上げるだけでなく、それに見合う体験や価値を提供すること。これが大切なのです。
たとえば、空間づくりやスタッフ教育、オペレーションの工夫、ブランド価値の演出など、考えられることはさまざまあります。これらを組み合わせて、初めて「納得感のある価格」になります。
私たちが20年にわたって焼鳥店を続けてこられたのは、この点を徹底してきたからだと考えています。
原価率の落とし穴に注意

もうひとつ、値上げにはポイントがあります。それは、いくら値上げをするかということです。
ここでは、よくある「値上げの勘違い」について説明します。飲食店を経営していると、「仕入れ価格が上がったから、その分だけ値上げしよう」と考える人が出てきます。しかし、この考え方には注意が必要です。
以下、焼鳥を例にして解説します。
【値上げ前】
鶏肉:1kg=1,000円
1kgから焼鳥10本作れる場合、1本あたりの原価=100円
これを1本350円で売ると、
原価率=約28.5%となります。
【値上げ後】
仕入価格が上がり、鶏肉1kg=1,500円になったとします。
1本あたりの原価=150円(+50円)
単純に50円値上げして、1本450円で販売すると、
原価率=約33.3%となります。
「値上がった分はしっかり転嫁した」と思うかもしれませんが、原価率は4.8%悪化しているんです!
この差は決して無視できるものではありません。残念ながら、これに気付かない素人が多いのも飲食店も特徴です。
飲食店の経営は「数字で管理する」ことが大前提です。その「数字」とは、価格ではなく、「%(割合)」です。
「50円の値上がりに対し50円値上げしたからOK」と考えていると、知らず知らずのうちに利益を圧迫してしまいます。多くの個人店がここに気づいていません。そしてこれこそが、飲食店が経営的に苦しくなる大きな原因のひとつなのです。
値上は賢く、恐れずに
仕入れ価格が上がったのに値上げに踏み切れないという考えは、インフレ時代には合っていません。それは30年に渡る失われた時代の生き抜き方であり、時代遅れです。発想を変え、「値上げ=悪」という考えを捨てましょう。
そして「価格に見合う価値をつくる」という視点をもって、店舗全体の見直しに取り組んでみてください。
数字を理解し、顧客の気持ちを考え、現場で工夫を重ねる。
このバランス感覚こそが、これからの飲食店経営に求められる力です。