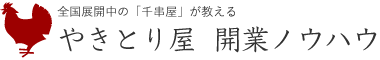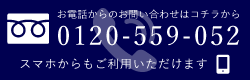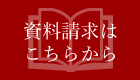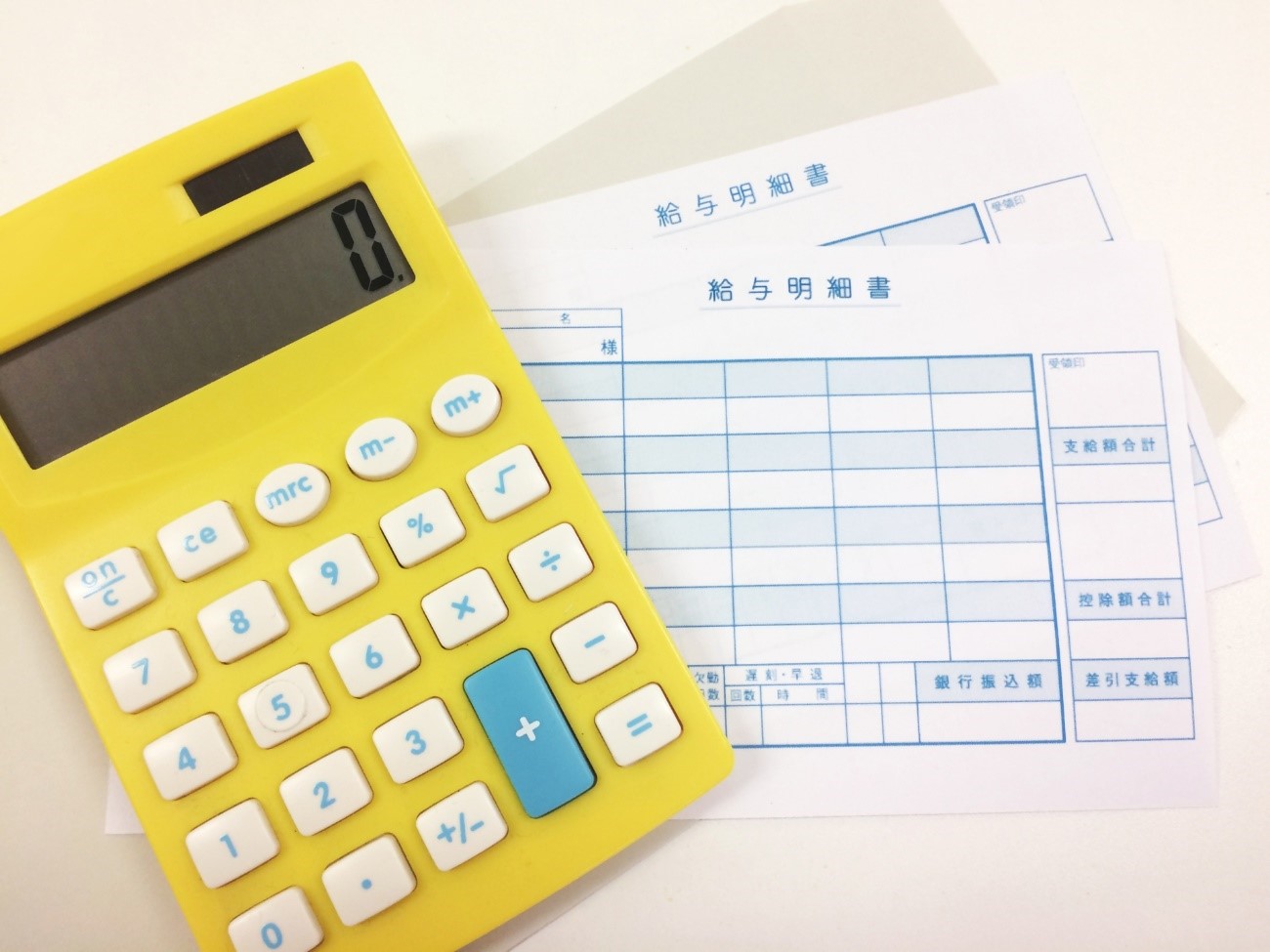飲食店における店長の重要な業務の中に、労務管理があります。ここには、さまざまな法律が絡んでいるだけでなく、ひとたび運用を間違えれば悪評が立って、人が集まらないことになってしまいます。非常に難しい内容ですが、基本を抑えてしっかり運用をしていきましょう。
労務管理に関する法律
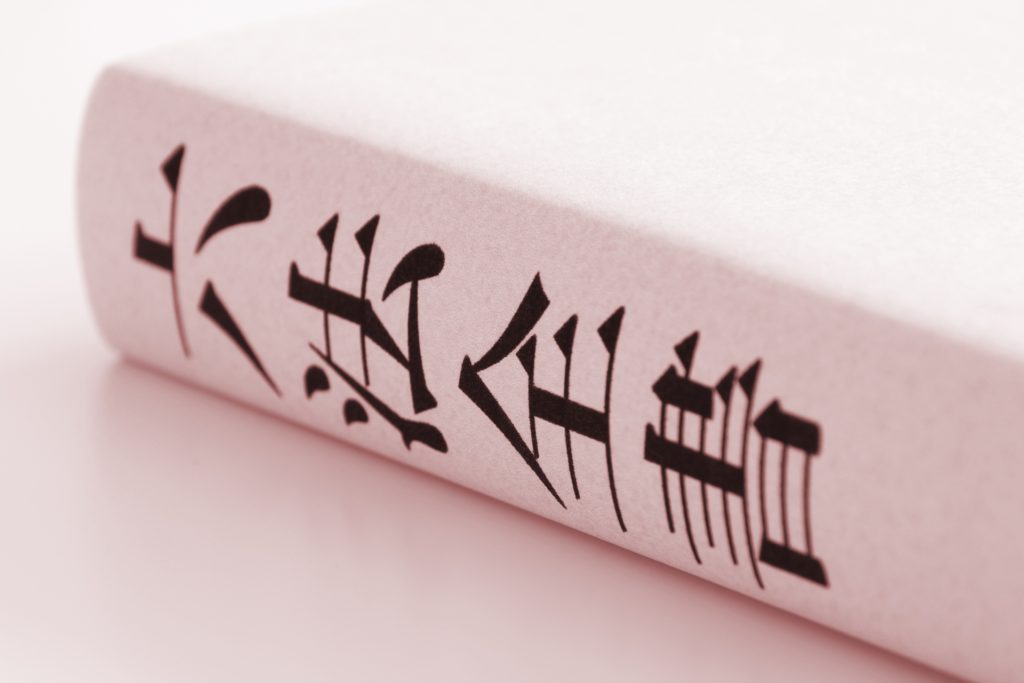
労務管理に関する法律には以下のようなものがあります。
労働関連法規
- 労働基準法:解雇、賃金、労働時間
- 労働安全生成法:健康診断など
- 最低賃金法:最低賃金など
- 高齢者雇用安定法:定年・雇用延長法
- 男女雇用機会均等法:妊産婦、セクハラなど
- パートタイム労働法:定時制乗務員など
労働保険法規
- 労働者災害補償保険法:保険など
- 雇用保険法:給付、保険料、助成金など
社会保険法規
- 健康保険法:被保険者、給付、保険料など
- 介護保険法:被保険者、給付、保険料など
- 厚生年金保険:被保険者、給付、保険料など
いかに多いかがお分かりでしょう。これら、すべてを守らなければならないのです。
では、主要な法規を個別に見ていきましょう。
労働基準法と36協定
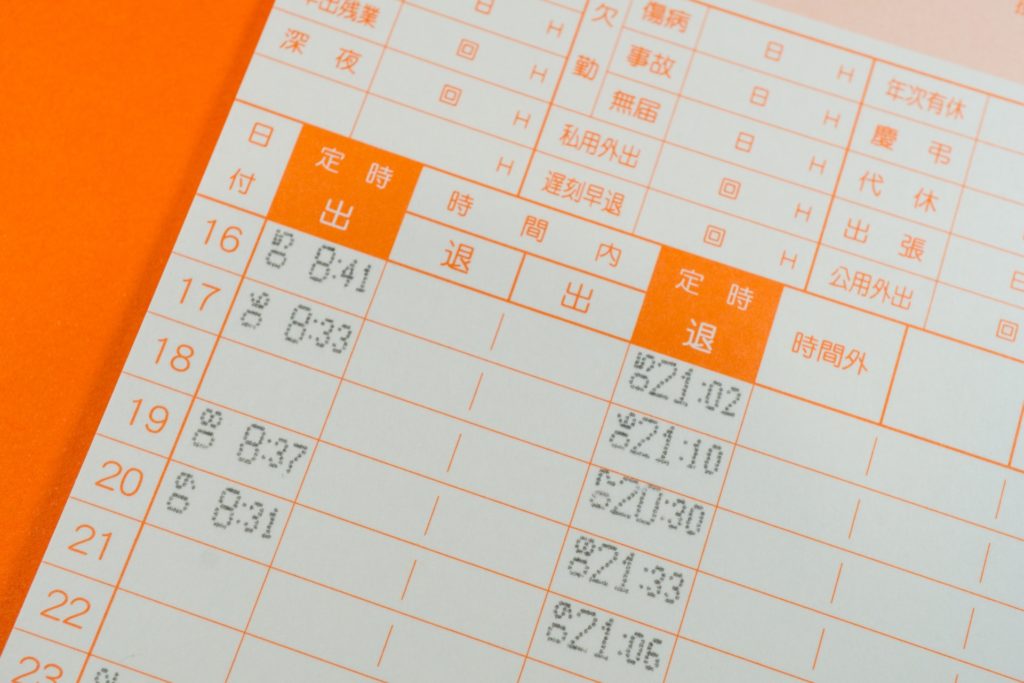
労働の基本となるのは、労働基準法です。
これによれば、以下のようになっています。
労働時間は、1週間40時間、または、1日8時間(休憩時間を除く)
休日は、原則、毎週最低1日。例外として4週間に最低4日
このため、労働外時間や休日労働をさせる場合、36協定を締結し届け出なければなりません。
①時間外または休日の労働をさせる必要のある具体的事項
②業務の種類
③労働者の数
④1日および1日を超える一定の期間について延長することができる時間。
または、労働させることができる休日
⑤協定の有効期間の定め(労働協約による場合を除く)
ただし、36協定を結んだからと行って、無制限に働かせられるわけではありません。当然、上限があります。それが以下です。
・1ヶ月:45時間
・3ヶ月:120時間
・1年:360時間
(他にも細かな規定があります)
みなし残業代とみなし深夜勤務手当
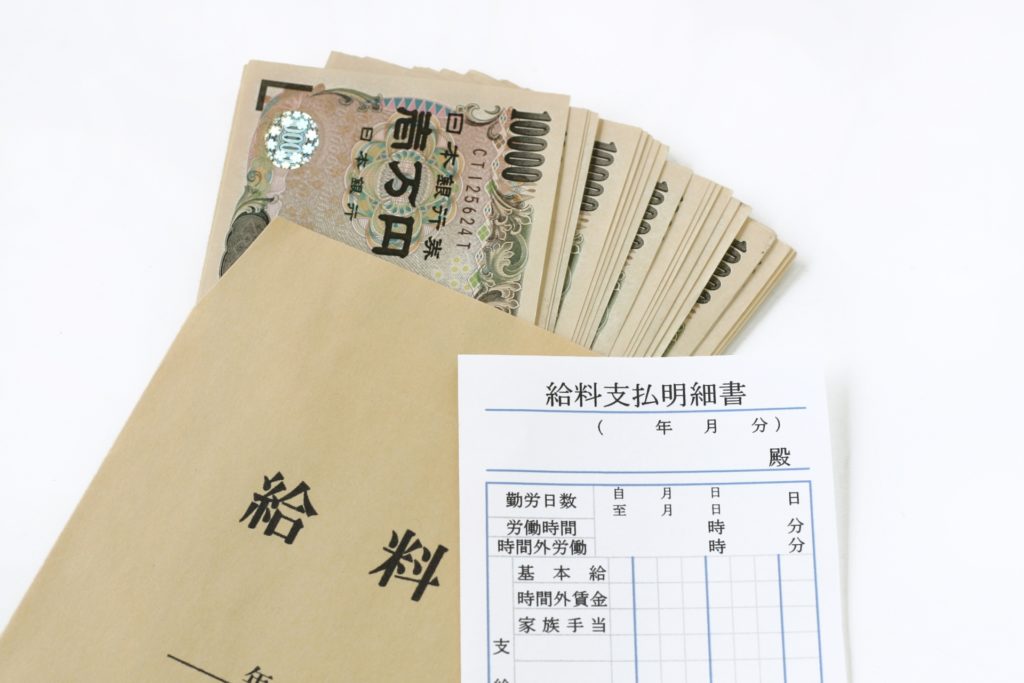
飲食店では、深夜勤務(夜10時~朝5時までの勤務)や残業代(週40時間を超える時間外労働)が発生したり、休日に仕事をするケースが多くあります。そのような場合、あらかじめ「固定残業制度」を採用することで、わざわざ計算をしなくてもよいこととなっています。これを「みなし残業時間代」などを言います。
注意していただきたいのは、みなし残業時間代を払ったから、それ以上は支払わなくてもよいとう意味ではない点です。あくまでも、みなし残業時間やみなし深夜勤務手当を超えて仕事をした場合、該当分は支払わなくてはなりません。
最低賃金は毎年更新される
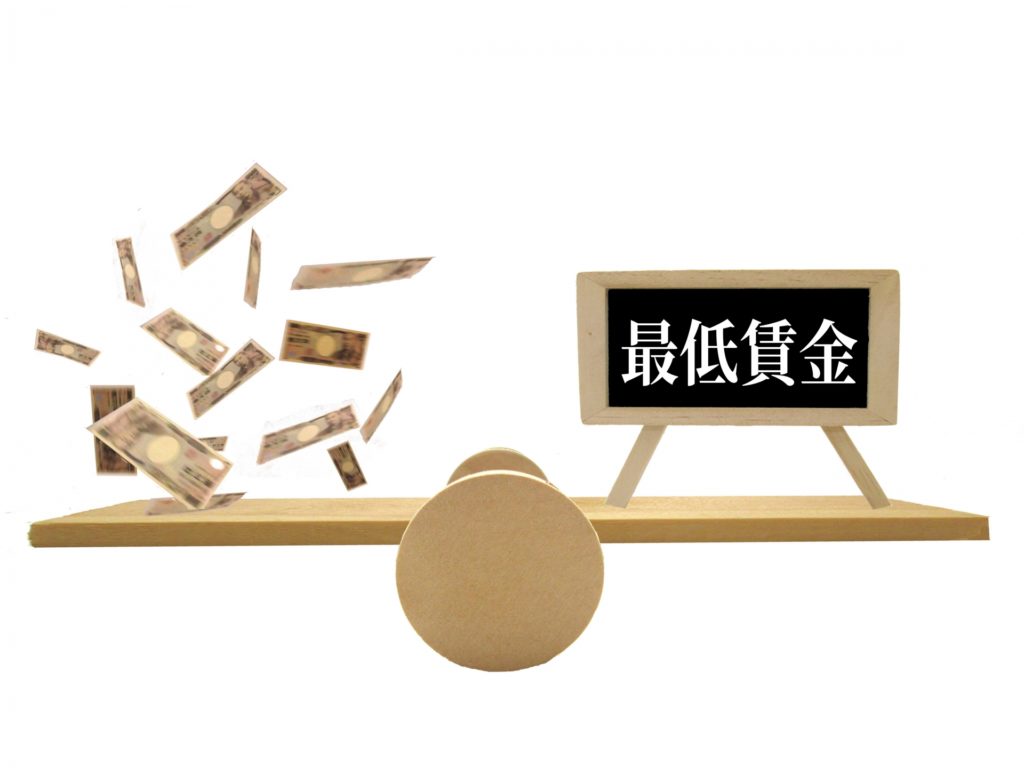
アルバイトを雇うとき、最低賃金を下回る金額提示をしているケースを見かけます。これは人不足の原因となるほか、法令違反となるため、すぐに対処しなければなりません。
最低賃金とは、最低限支払わなければならない賃金のこと。「研修中だから」「アルバイトだから」といった区分はなく、雇用関係を結んだすべての人が対象となります。つまり、この金額以上のスタート時給を設定しなければならないということです。
もし、最低賃金以下の時給で働かせた場合でも、最低賃金で契約したものとみなされ、不足分を支払わなければなりません。
最低賃金は毎年改定されており、10月に翌年分が発表されます。さまざまなところで見ることができますが、厚生労働省のサイトで確認するとよいでしょう。
厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
違反が見つかれば、労働基準監督署から是正勧告がくる
労働基準法が守られているかを監督するのが、労働基準監督署です。もし、労働者と従業員がトラブルを起こした場合や、辞めた後に法令違反を訴えた場合などに、労働基準監督署が立ち入り検査を行います。これを「臨検」と言います。この際、違反が認められると「是正勧告書」が交付され、指定の日までに是正をしなければなりません。
一方、店舗運営の現場では、人手不足から雇っている店長や社員に休日を取らせられなかったり、残業が多くなったり、休憩をきちんと取らせられなかったりします。しかし、それでは、ますます厳しくなる世間の目や行政の方向に太刀打ちできません。飲食店は、何とかして法律を守りながら、経費コントロールをしなければ行けなくなっているのです。
経営者は労務管理をしっかりと行い、法令違反がないようにしてください。