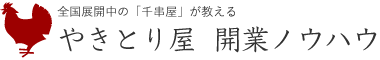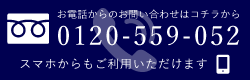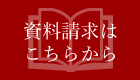店舗が健全に運営されるためには、店舗管理者であるオーナーや店長がさまざまな業務を効率よくこなさなければなりません。ここでは、店長が仕事をする上でどのような心構えを持って取り組むべきなのかを見ていきます。
Contents
常に全オペレーションを把握しておく
店長が営業中にやるべきことは、自らがオペレーションをスピーディにこなすことではありません。基本的に各ポジション(キッチン、ホール、パントリー)の監視やフォロー、店舗全体がスムーズに運営されるための全員への指示だし、滞りの解消のためのフォロー等が主な業務となります。
このためには、当然ながら、全オペレーションが把握できていなければなりません。オーダーが重なり商品が出ないからと言って、焼き鳥を焼くことに没頭してしまったのでは、他の場所でも滞りが発生し、結果的にお客様の不満につながってしまうのです。
店長だけが、店舗全体のオペレーション能力を高めることができ、それを通じて、全スタッフから信頼される存在になることができるのです。いかなる時も、そのことを忘れてはなりません。
的確な指示出し

ピークタイムは、すべてのスタッフが、たくさんの仕事を抱えながら作業しています。そういった時間帯こそスタッフの動きをしっかりと確認しながら、無駄なく仕事ができるための指示出しをしなければなりません。店長は、店内が忙しいときこそ全体の把握に努め、全員のベストパフォーマンスを発揮させるべきなのです。
目を配るのは、キッチン、ホール、パントリーなどで仕事をするスタッフはもちろん、お客様にも目を配り、その時々で最優先してやるべきことは何なのかを考え、仕事を指示出しをします。店が円滑に回るか回らないかは、指示出しで決まるといっても過言ではありません。
場合によっては店長が率先してオペレーションに参加することもあるでしょう。ただし、店長である以上、1ワーカーとして作業に没頭したのでは全体が見えなくなってしまいます。作業をしながらでも指示出しをすることを心掛けてください。
また、新人アルバイトがいるときは、全員が全力で仕事をすべきなのに、指示がないために立ちすくんでいることがあります。このような場合、新人アルバイトは立場がないと感じており、「つらいから辞める」ということにもつながります。そういったことがないように配慮しなければなりません。忙しい時間はトレーニングを行えませんので、事前に必要なことを教え、「忙しい時間はこれをやる」などと指示しておくことも有効です。
指示出しはピークタイムだけではありません。余裕のある時間に何をすべきか。店舗が忙しくなるピークタイムに向けての準備を進めるのか、顧客満足を上げるための掃除をすべきかなど、1日を通して円滑な運営ができるように全体をコントロールすることも店長の重要な仕事です。
営業上の問題点の発見と解決

日々、営業をしていると、なにかと問題点が出てきます。
例えば、洗い場の動線が悪いためにスタッフの動きが止まってしまうとか、キッチン内の食器の配置が悪いためにスピード提供の妨げになっている、といったことです。簡単に解決できるものもあれば、大がかりな変更が必要なもの、棚など何らかの購入をしないと解決しないものなど、いろいろあるでしょう。
もちろん、これらの改善は重要ですが、何より、「店長が問題点に気づく」ことから始まることを忘れてはなりません。ただなんとなく「商品提供に時間がかかる」と思っていたり、スタッフの動きを漫然と見ていたしするだけでは問題点が見えてきません。
常に店の状態を良いものにするために観察し、問題点を発見、解決する意識を高く持ち、アンテナをはっておくようにしてください。
店長が模範となってルールを徹底する
社会にはルールがあります。みんなが好き勝手なことをやってしまうと社会が成り立たなくなってしまいます。そうならないために、ルールが存在しているのです。そして、同じように、店にもルールがあり、それを守れない人と一緒に仕事をすることはできません。
社員やアルバイトが遅刻・欠勤を繰り返したり、身だしなみが悪かったり、お客様を無視した行動をしたり、自分たちのことを優先する場合には、店長として厳しく注意しなければなりません。
そして何より、店長であるあなた自身が決められたルールを守っていないと、スタッフの信頼を得ることができず、ついてきてくれることはありません。ルールを守る店舗を作るには、まずは店長自身が、常にスタッフの模範になっていること。これが店長の最低限の務めといえるでしょう。
商品クオリティーの維持

飲食店では、お客様の商品に対する期待は大きく、その期待に応えていくことが売上げ確保の鍵を握っています。その一方で、キッチンで調理を担当するのはアルバイトが中心といったことも珍しくありません。その中には、料理を作るのが初めてというスタッフもいるでしょう。また、外国人で、日本の調理法や味わいを理解できていないケースも増えています。
それでも飲食店では、アルバイトに任せなければ店が回らない現実があります。その場合、信頼して任せることも大切ですが、その前に十分なトレーニングを行うことに加え、商品提供の前に、細かなチェックをすることでクオリティーを一定に保つことが重要です。
雑な盛り付けの料理やレシピと違った味付け、火が完全に入っていないものがないか。そういった商品は、お客様に提供してしまう前に、十分にチェックする必要があります。
「忙しいから」とか、「まだ新人だから」などといった理由は、お客様には一切関係ありません。妥協を許さず、厳しい目でチェックをしなければ、お客様の満足は得られないのです。
ワークスケジュールの立案

ワークスケジュールは、店長レポートの作成やシフトのコントロール(人員調整)、月々の予定や、自分や社員の休み、お席の予約状況、新人トレーニング、近隣のイベントなどを踏まえた上で立案していきます。
チャンスロスを起こさず、スタッフの必要以上の負担をさせないために、店内だけの情報だけでなく、外的要因までを把握し、ワークスケジュールを作成するようにしてください。
また、店長になると管理しなければならない物事が多くなります。出席するべき会議も増え、販促の計画なども立てなければならず、業務はどんどん増えていきます。当然、それらすべてをこなしてこそ店長といえるのですが、ただ闇雲にやっていては時間ばかりかかってしまって効率的に物事を進めることができません。何事にも計画が必要です。それらの業務を行う時間も考えて、ワークスケジュールを立案するようにしてください。
クレーム対応とリスクマネジメント

店舗運営において、クレームは避けて通れない課題です。クレームが発生した場合、オーナーや店長に求められるのは、「迅速な対応」と「真摯な姿勢」です。どれほど商品や接客に自信があったとしても、お客様が不快に感じたという事実に真摯に向き合わなければ、信頼を損なう結果につながります。
重要なのは、クレーム対応を「ピンチ」としてではなく、「信頼回復のチャンス」と捉える姿勢。まずはお客様の言い分を遮らずに丁寧に聞き、そのうえで誠意をもって謝罪し、必要な対応をとることが基本となります。
また、その場限りの謝罪だけで終わらせるのではなく、原因を明確にし、スタッフと共有し、再発防止に向けた対策を講じることが肝心です。
クレーム対応の質は、店舗のマネジメント体制全体に影響を与えます。店長が冷静で的確に対応する姿を見せることで、スタッフは「問題が起きても店長がいるから安心だ」と思えるようになります。逆に、言い訳でごまかしたり、スタッフのせいにする姿勢は、スタッフの士気を下げるばかりか、お客様の不信感も招きます。
さらに、クレーム対応だけでなく、未然にトラブルを防ぐ意識も不可欠です。
たとえば、予約の重複やアレルギー情報の見落とし、スタッフのまずい対応など、トラブルにつながるリスクは身近にあります。それらを予測し、事前に対応策を用意しておくことが、店舗を守る強固な基盤となります。
店長は、「何かあったら動く」のではなく、「何か起こる前に察知する」アンテナを常に張っておくことが求められます。それが、店舗とスタッフ、そしてお客様を守る最前線でのリーダーの役割です。
また、カスタマーハラスメントが起こったら、しっかりとスタッフを守り、毅然とした態度をとることも重要です。
売上と数値の管理

現場のオペレーションや接客の質に加えて、「数字を見る力」も強く求められます。日々の売上、原価、人件費といった数字やパーセンテージなどの指標を把握することで、店舗の状況を客観的に分析し、的確な改善策を講じることが可能になります。
基本は「日次・週次の売上把握」です。前日や先週と比べてどうだったか、予算との乖離はないか、曜日や天候、イベントなどの要因も含めて分析することで、売上の動向を的確に読み取ることができます。単に「売上が良かった(悪かった)」で終わらせるのではなく、「なぜその結果になったのか」を深彫りする姿勢が重要で、店長としての成長にもつながります。
次に重要なのが、「原価率」と「人件費率」です。利益を増やすには、コストを適切に抑えることが不可欠。特に人件費は、シフトの組み方ひとつで大きく変動します。ピーク時間に人が足りないとクレームや機会損失が発生し、逆に暇な時間に人が多すぎると無駄な支出につながります。数字を見ながら適正な人員配置を行う力は、店長として非常に重要なスキルです。
また、数字は「経営判断の材料」であると同時に、「スタッフへの共有ツール」にもなります。「今月は客単価が少し下がっているから、おすすめメニューをもう一度アピールしよう」など、現場にわかりやすく伝えることで、スタッフの意識を売上に向けることができます。数値をオープンに共有し、皆で目標を追いかけるチーム作りも、店長にしかできない役割です。
では、店長自身が数字に強くなるために何をすればよいのでしょうか。
まずは、日々の記録と振り返りの習慣を持つことが重要です。売上データ、クレーム件数、スタッフの遅刻・欠勤の記録など、すべてが店舗改善のヒントになります。
「数字は苦手」と思い、積極的に数字を見ない人もいますが、店舗をよりよくするための“言葉”として受け止めていくことが、管理者としての力量を高めてくれるのです。責任あるポジションにいるわけですから、苦手意識は一刻も早く克服してください。